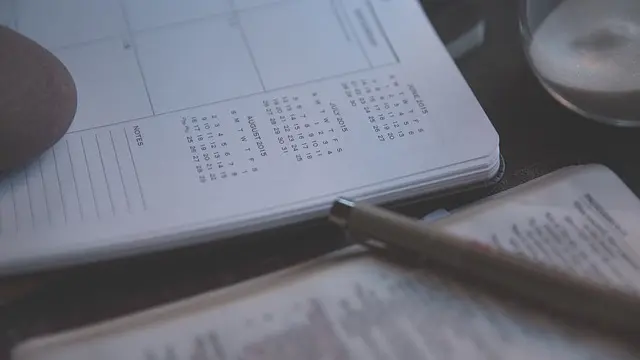世界史通史
クリップ(17) コメント(3)
7/10 13:41
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
本番強し
高3 東京都 早稲田大学商学部(70)志望
高3早稲田志望です。現在ナビゲーターを使って流れを把握してから、壁に向かって生徒がいるつもりで教えるような気持ちになって頭に定着させてます。流れは結構入ってくるのですが、単語、年号をあまり覚えられないのと、ナビゲーターには全然地図が載ってないので、そこら辺があいまいです。ナビゲーターの他に、並行してやった方がいいことはありますか?
回答
ひろ
慶應義塾大学法学部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
1. ナビゲーターの特徴と問題点
ナビゲーター良い参考書ですよね。流れを把握するのに最適な参考書だと思います!
しかしながら、ご指摘の通り、単語や年号、地図や資料については弱いというのもナビゲーターの特徴です。これはナビゲーターという参考書の性質を鑑みれば、当然とも言えます。
ナビゲーターは山川出版で、いわゆる山川世界史(青い教科書)をより分かりやすく、話口調で噛み砕いた講義系参考書です。したがって、学校の授業に置き換えると、「教科書+先生の説明」のようなものと考えて下さい。学校の授業で勉強している時、教科書と先生の説明のみで勉強しているでしょうか?通常、それらに加えて、手元にノートや資料集があると思います。自分で勉強する際にも、同様に考えてみれば、ナビゲーターだけでは不十分であることが分かります。
2.ナビゲーターの利用法と併用すべきもの
では、どうすれば良いか?学校の授業と同様に考えてみましょう。
まずは資料集です。これは年表や地図、家系図などの図や資料、写真など、参考にすべきものがたくさんあります。補足的情報や整理、縦・横の繋がりの把握に役立ちます。これらに不足しているナビゲーターに、資料集は必須です。必ず、傍において適時参照すべきです。
学校で配布されているものなら問題ないと思いますが、もし所持していなければ「タペストリー」がお勧めです。
次にノートです。ノートの役割は、教科書や説明、資料集で得た膨大な知識を整理します。頭にインプットする際、教科書ベースで記憶している人は少ないと思います。よりいらない部分を切り落とし、秩序立てられたノートベースで記憶する必要があります。また、ノートには情報を一元化する媒体としての役割もあります。問題演習を通して得られた新たな知識をどんどん書き込み、入試直前まで参照する媒体として、ノートは最適です。
余裕があれば1からノートを作るのも良いですが、非効率的です。なので、「山川 学習ノート」などの書き込みノートがお勧めです。また、学習ノートは山川出版なので、ナビゲーターとも相性が良いです。
補足的に、必要であれば「山川 用語集」を置いといても良いと思います。これは、手元に置いておき辞書的に用います。用語を思い出せなかったり、より詳しく知りたい場合に参照して下さい。
3. 世界史の勉強法
以上で、ナビゲーターの利用法と併用すべきものを記述しました。ナビゲーターはいわばインプット用教材です。ナビゲーター、資料集、ノートを用いてインプットが終わったら、アウトプットをしましょう。
アウトプットは様々な方法があります。実践されている通り、人に説明するように口に出すのもその一つです。
一応、僕がお勧めする方法を以下に書いておきます。
①1回分、ナビゲーターを読む。この時、資料集で地図等を確認しながら読む
②ある程度覚えたら、学習ノートを解いてみる。これが1度目のアウトプット。また、オレンジペンを使って復習できるように、1度目は書き込まず別紙に解く。
③ナビゲーターを見ながら、オレンジペンで学習ノートに書き込む。
④次の日、オレンジペンを赤シートで隠して、復習
⑤忘れた頃に、復習
⑥1テーマ分(ギリシアやローマなど)終わったら、基本問題集(「ツインズ・マスター」や「30テーマ世界史問題集」など)で再びアウトプット。
これが一連の流れです。これを通史で行って下さい。
世界史学習のポイントは短期間で、集中することです。ダラダラとやっていると、すぐに忘れてしまいます。長くとも、3ヶ月で通史を一度やってみて下さい。次は1ヶ月でもう一周して下さい。さらにその次は10日でもう一周して下さい。このように最終的には、すぐに1周できるようにしましょう。
こうして知識が定着したら、抜け・漏れを防止するために、一問一答を用いると良いでしょう。
また、この段階で、共通テストレベルの実践問題集、志望校のレベルの参考書をやると良いでしょう。
世界史は社会科目で最も範囲が広いですが、定着すると最も点数が安定します。辛抱強く頑張りましょう!少しでも参考になれば幸いです!
また、質問等あれば、メッセージやコメントお待ちしております!!
コメント(3)
本番弱い
7/10 14:49
詳しい返信ありがとうございます!山川出版社のまとめノート買ってみようかと思います!自分は早稲田大学志望なのですが、そのようなレベルの高い大学で出されるハイレベルな知識はどのようにインプットしてけば良いでしょうか
本番弱い
7/10 14:57
あとそれか、ノートじゃなくて時代と流れで覚える!用語のやつでインプットしようか迷ってます。ナビゲーターを一読してからそちらでインプット、アウトプットは書いてくださったやり方でというのはどうでしょうか
ひろ
7/11 7:29
「早慶レベルの用語のインプットはどうするか?」
→早慶などの難関私立でもナビゲーター、用語集、資料集、斉藤の一問一答で、8割カバーできると思って下さい。残りの2割に注力してしまいがちですが、8割の部分を完璧に抑えたほうが良いです。また、他の苦手科目に時間を割くのも良いでしょう。
ただ、タテからみる」や「ヨコから見る」、「一度読んだら忘れない 経済編」などの各国史、テーマ史をやっておくのは、余力があればやっても良いと思います。
あとは過去問や問題演習を通して得た新たな知識は、情報一元化媒体に集積していって下さい!
「時代と流れで覚えるをノートの代用としてどうか?」
→良いと思います。
ノートの役割は、①情報を整理する、②インプット教材として利用、③情報一元化の媒体、④1回目のアウトプット、以上4つです。
この参考書は①、②、④を満たしています。③も頑張れば書き込めるかもしれません。
要は、ノートのように余白があり、カスタマイズ余地が大きいものと、この参考書のようにきっちりと情報がまとまっているもののどちらが良いかです。
他にもそれぞれ良い点、悪い点があると思うので、しっかり比較検討して選ぶのが良いかと!