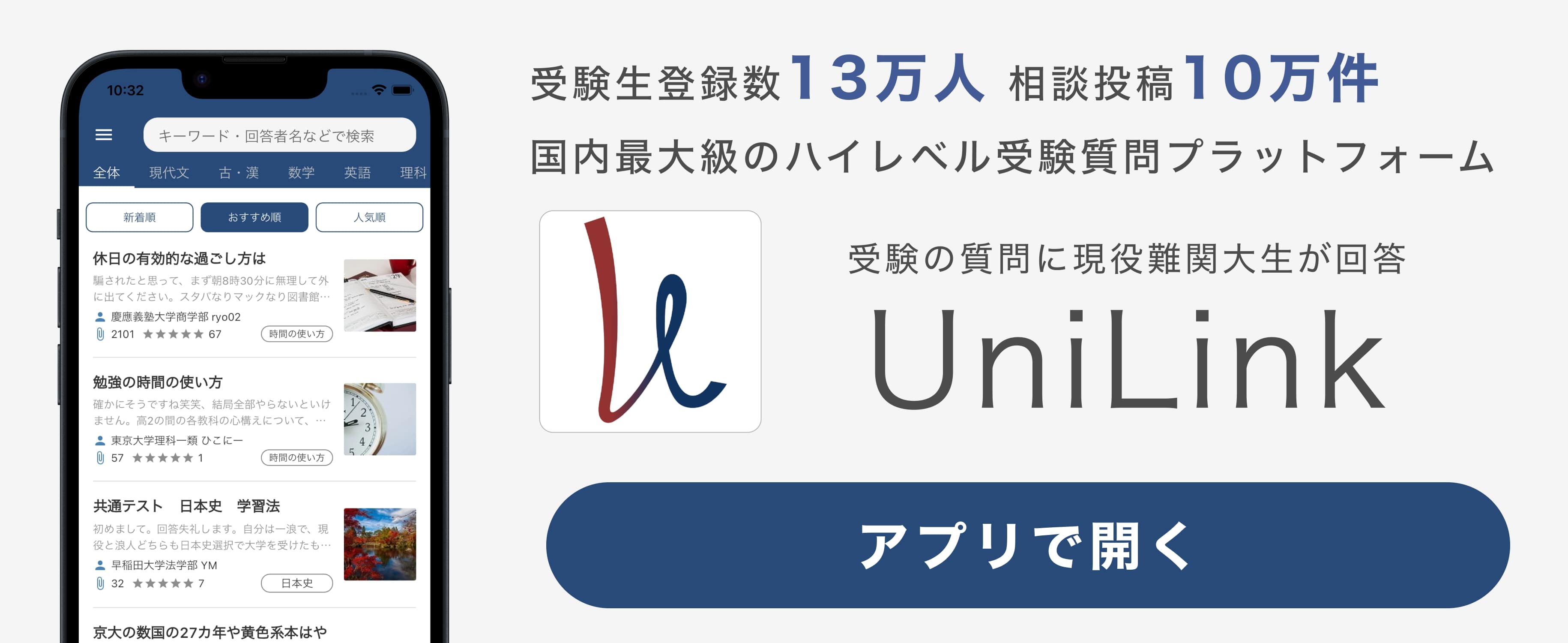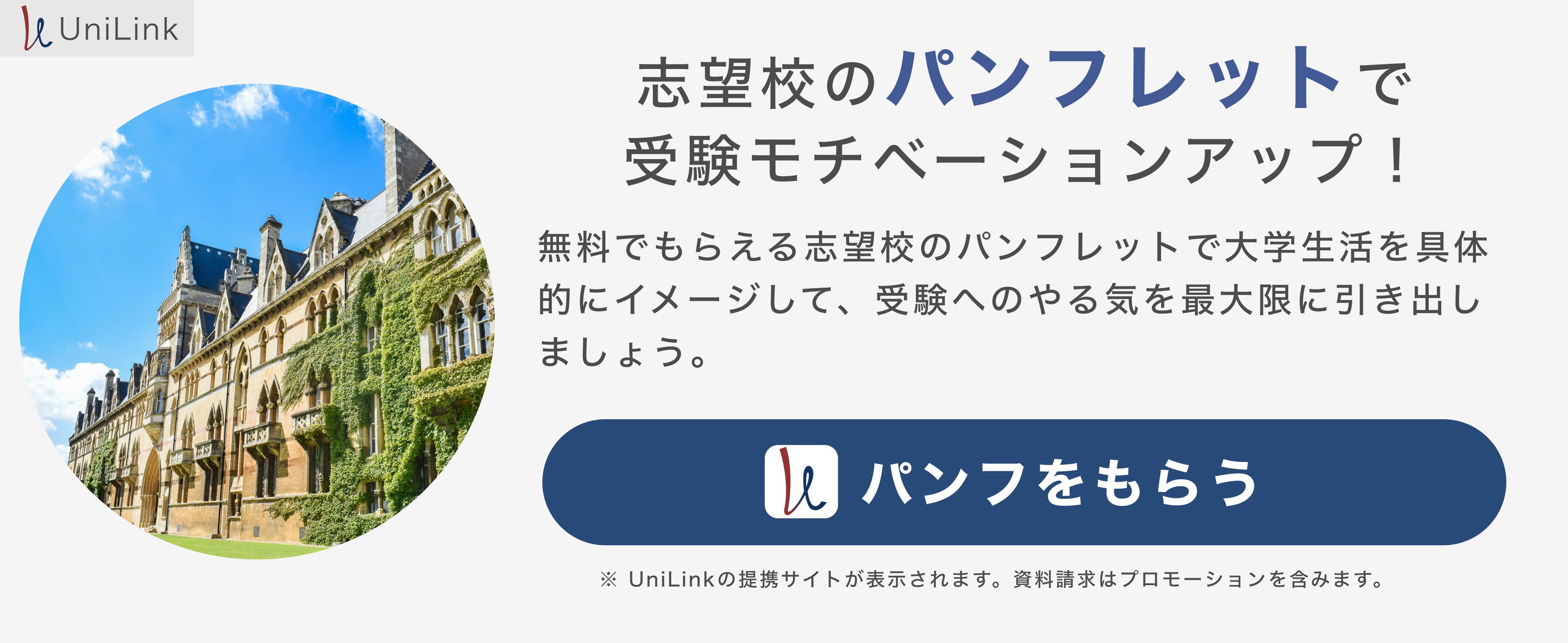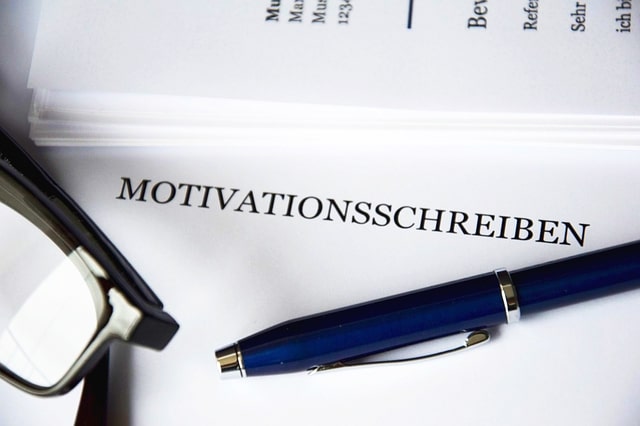質の良い勉強
クリップ(8) コメント(1)
3/16 11:43
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
S.Saito
高1 北海道 早稲田大学志望
よく質の良い勉強が良いと聞くのですが、どのようにすれば質が上がるのでしょうか?
回答

umeadi
早稲田大学社会科学部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
勉強をするときはしっかりと集中する。オンとオフの切り替えをしっかりする。
同じことをやるにしてもそれを効率的にやる。例えば日本史の勉強をするにしてもただ単に覚えるのでなく事柄を関連付けたりしながら覚えたり、英文の中で英単語を覚えたりなど。
無駄なことはとにかくしない。
こんな感じだと思います。質の良い勉強とは中々難しいですね^^;
コメント(1)
S.Saito
3/18 18:48
ありがとうございます!