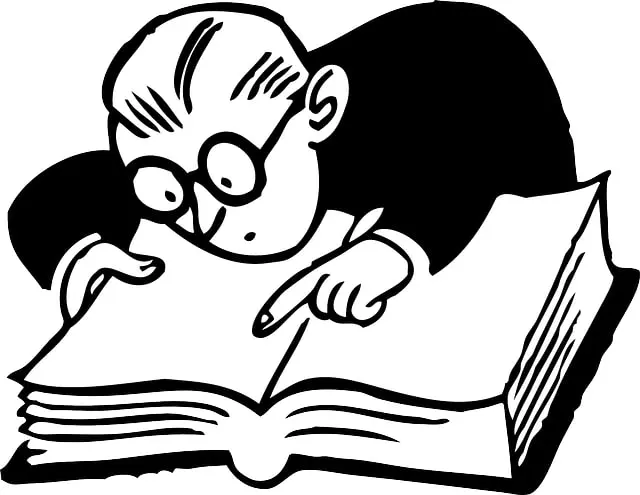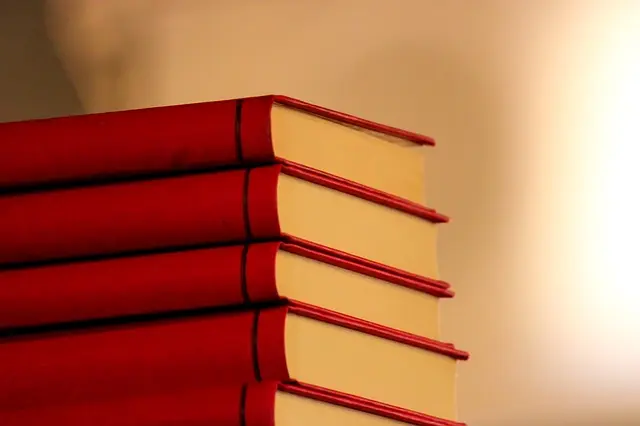復習法
クリップ(33) コメント(1)
1/4 2:05
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
のん
高3 三重県
授業があった日の復習とは、何をすることなのですか?
また、復習をするために学校の課題を早く終える方法を知りたいです。
回答
taka37
早稲田大学スポーツ科学部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
復習しなさい
と皆言われてきたけど、その真意は、復習する事で定着率が良くなる事 です。
1回で聞いてわからなかったことを時間かけてやる事も復習かもしれないけど、分からないを分かるにするのは学校での作業。習った事は授業中に全部分かるようにする。分からなかったら先生に聞く。
家に帰って、自分の力でもう一度自分でやってみる。
これが復習。
これが一番効率の良いやり方。
分からない問題ノートを作ると効率的やで。
頑張れ。clipしてね!
コメント(1)
のん
1/5 11:19
自分ができていないところ、足りないところを復習でしっかり補えるように復習ノートを使って頑張っていきます。
ありがとうございます!
あと1年、日々の積み重ねを大切にしていきます。