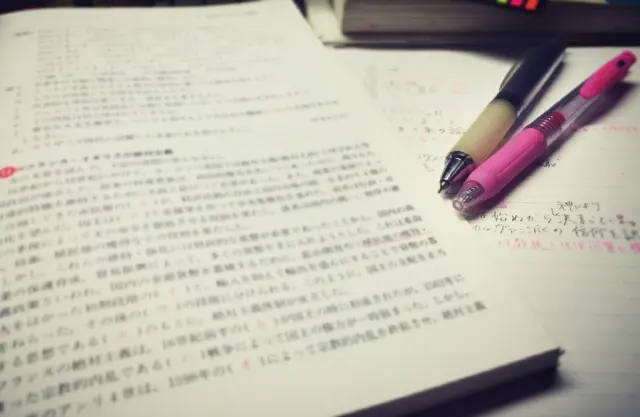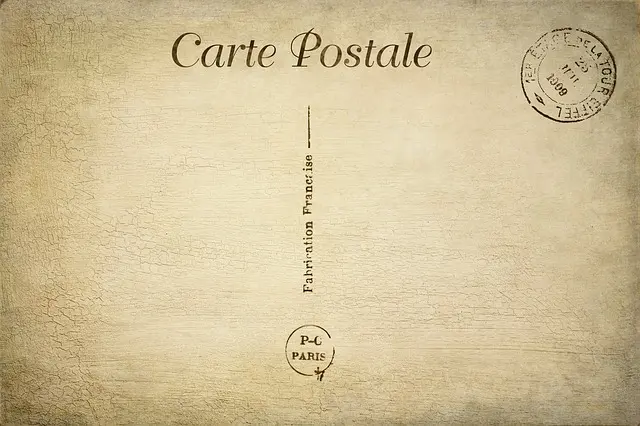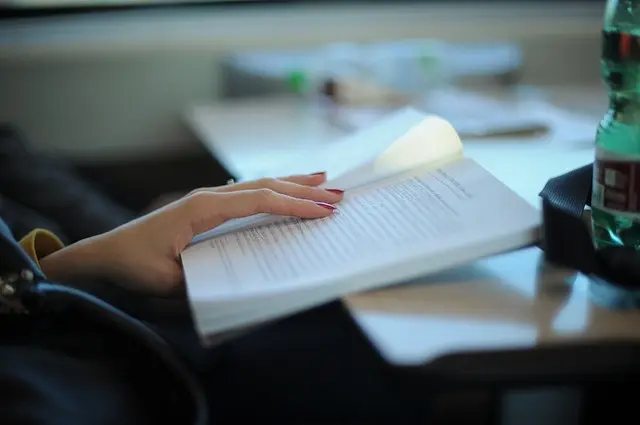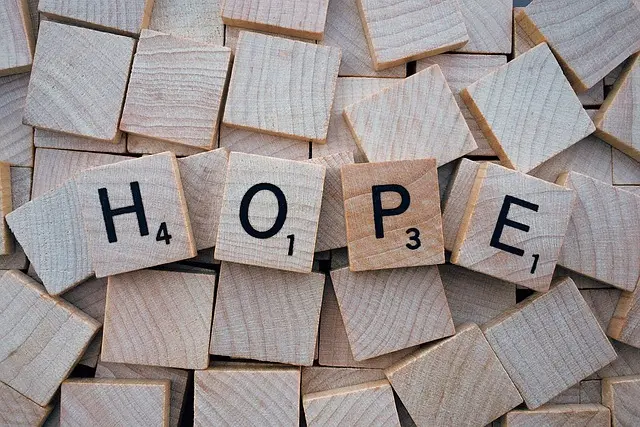先輩方から英語の問題集についてご意見を承りたく存じます。
おはようございます。日々の勉強おつかれさまです!
慶應義塾大学文学部のネギタコ焼きと申します。よろしくお願いします。
今回は、①英語の学習の順番 ②おすすめの教材 ③時間の目安 ④各分野の勉強法
について書いていきたいと思います。少々回答が長くなってしまいますが、ご容赦ください。
まず①について
・英語の学習は、以下のような流れで進めていきます。
・単語・熟語+文法→英文解釈→長文→長文の多読+分野別対策(英作文、文法正誤、口語表現・会話文、発音・アクセント等)→志望校の過去問
・まず、単語と熟語、それに文法問題集に取り組み、英語力の土台をつくります。
・次に、英文解釈に取り組むことで、学習した語彙や文法が英文の中でどのように使われているのかを知り、英文の読み方を習得します。
・そして英文解釈をひと通り終えたら、長文の問題集に取り組み、長文読解力を養成します。
・それを終えたら、早慶上智の過去問を使い、様々な形式の問題を解いて、実戦力をつけます。そして同時に、自分の受験校の問題傾向に応じて、英作文や会話文等の対策をやっていきます。
・そして最後に、志望校の過去問に取り組み、本番に備えます。
次に②について
ここでは、各分野のおすすめの教材を分野別に紹介します。
〈単語〉
・システム英単語
・鉄壁
・英検1級(準1級)の単語帳《慶應の総合政策・環境情報,早稲田の国際教養、社会科学,上智の各日程等の難易度の高い語彙が必要な場合》
〈熟語〉
・解体英熟語《早慶を目指すなら、これ一冊で充分/慶應法学部志望は必携の一冊》
〈文法・語法〉
・頻出英文法語法問題1000《基礎から早慶レベルまでのレベルが網羅されているので、早慶志望ならこの一冊を仕上げればOK。解説も詳しい。》
・英文法の核《ポレポレの著者が書いたフォレストのような文法書。文法問題集でわからない部分があれば、これを辞書として参照するとよい》
・スーパー講義英文法・語法正誤問題(河合出版)《正誤問題対策の定番》
〈英文解釈〉
・基礎英文解釈の技術100《英文の読み方の基礎は、この一冊でひと通り身につく。基礎がついていない英文解釈の技術100と間違えないように注意》
・ポレポレ《早慶の英文を読むために必要なエッセンスが詰まった一冊。ほとんどの英文が読めるようになる。》
・英文読解の透視図《英文解釈の参考書では最高難度。ポレポレが肌に合わなかったり、早慶の難関学部を目指しかつ時間に余裕がある人向け》
〈長文〉
・解説が詳しく、自分に合いそうなものを選べばよい。
・一例として、ハイパー英語長文シリーズ,やっておきたい英語長文シリーズ,RISEシリーズ(Z会)。
〈英作文〉
・関正生の英作文のプラチナルール《英作文の書き方の基本がわかる》
〈口語表現・会話文〉
・英会話・口語表現の徹底トレーニング(プレイス)《過去問を解く前にやっておくとよい》
〈発音・アクセント〉
・音で覚える発音・アクセント《頻出事項が整理されて掲載されており、短時間で効率よく学習できる。慶應法学部志望にはオススメの一冊》
〈多読〉
・速読英単語標準編・上級編
・早慶上智の過去問《自分が受験しない学部の問題を中心に》
そして③について
・これは、人によって進み具合が異なるので、なんとも言えませんが、①で説明したことを基準にすると、長文演習までを高3の夏休みが終わるまでに、9月から多読演習と分野別対策、11,12月から志望校の過去問をはじめるとよいと思います。
・自分の勉強の進み具合を見て、予定を調整してください。大事なのは、1つ1つの学習をしっかり自分のものにすることです。
最後に④について
これも②と同じ要領で、各分野到達目標とともに書いていきます。
〈単語と熟語〉
★見出し語を見たら、瞬時に意味が答えられる。
*1000個の単語を暗記すると仮定します。
①1000個の単語を100個ずつ10パートに分ける。
②1パート目を3日間繰り返し暗記。
③2パート目も同様に。
④最後のパートまで暗記する。
⑤すぐに2周目に入り、同じ要領で繰り返し暗記。
⑥★の状態を目指し、繰り返し暗記する。
⑦定期的に復習し、★の状態を維持する。
*慣れてきたら、1パートの単語数を200個にするというように、1パートあたりの単語数を増やすとよい。
*熟語も同じ要領で。
〈文法・語法〉
★すべての問題を理由づけて答えられる。
*20章から成る問題集に取り組むと仮定します。
①全体を1パート4章ずつ5パートに分ける。
②1パート目を1週間で取り組む。適宜、手持ちの文法書を参照しながら解く。「どこを根拠に答えに至ったか」を意識。
③最後のパートまで同じ要領で。
④周回して、★の状態になるまで学習する。
*解く際は、紙に解答を書かず、目で1問解いたら解答・解説を読むとすると、1問にかかる時間を短縮できる。
〈英文解釈〉
★すべての例題で、英文の読み方を説明できる。また、例題の英文を英語の語順で理解し、スラスラ読める。
①例題を実際に書いて自力で和訳。
②「どのようなプロセスで英文を読んで、和訳しているか」という視点で解説を熟読し、自分のプロセスとのズレを確認する。
③書き込みのない英文を使い、②で学んだプロセスを口頭で再現する。
④例題の英文を口頭でスラッシュ和訳(3回)《スラッシュ和訳とは、英文を数個のまとまりごとに、英語の語順で訳していくこと。例 The president announced a concrete plan to carry out welfare reform.→大統領は発表した/具体的な計画を/行うための/福祉改革を》
⑤例文の英文を音読(7〜10回)
⑥すべての例題を上記の要領で行い、2周目に入る。2周目以降は、プロセス再現→スラッシュ和訳→音読で行う。
⑦★の状態になるまで、繰り返す。
〈長文〉
★すべての問題を理由づけて解くことができる。また、すべての英文を英文解釈の例題の英文と同様の状態にする。
①いつもどおり解く。
②答え合わせ
③「どこを根拠に答えに至ったか」という視点で、間違えた問題と根拠が曖昧だった問題を解説を読んで復習。
④英文解釈同様に、書き込みのない英文を使い、答えに至るまでのプロセスを再現する。
⑤本文をスラッシュ和訳+音読し、★の状態を目指す。
・過去問の使い方に関しては、ぼくの以前の回答を参考にしていただけると助かります。相当長くなってしまったので。
以上です。長文失礼しました。少しでも参考になれば嬉しいです。頑張って!