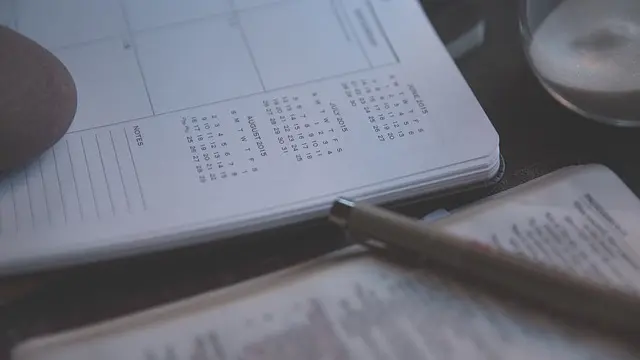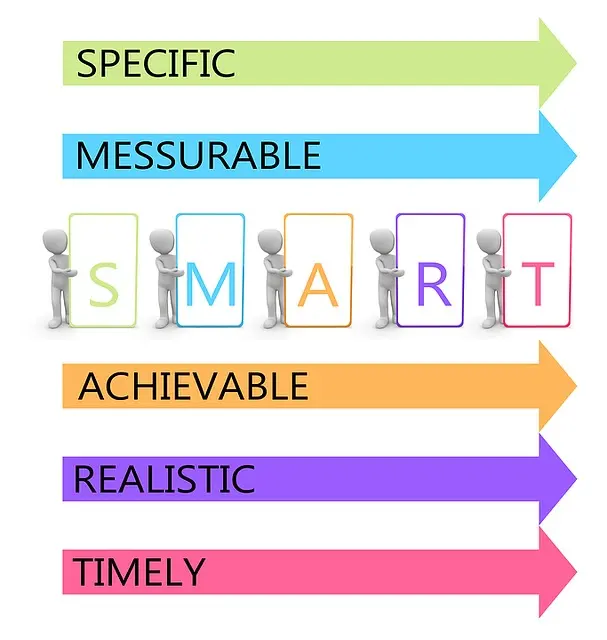平日と休日の勉強の時間割
クリップ(69) コメント(1)
6/22 5:30
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
ごぼう
高3 石川県 石川県立看護大学志望
高3の時、平日何時間、休日何時勉強していましたか?
そして、どのような時間割で勉強したかも教えていただきたいです。
回答
チュナ
早稲田大学国際教養学部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
平日は休日に比べて勉強時間が少なくなるので、私はインプットの作業、主に歴史をやっていました。部活もあったので、勉強時間はだいたい3ー4時間ほどです。インプットの作業というのは、塾での講義の時間も含みます。
まず私が欠かさずやっていたことは、塾や学校で歴史の授業を学んだら、必ず見直しをしていました。複雑な時代の時はノートにまとめたり、地図などを書いて整理していました。そうすると、次の授業がかなりわかりやすくなります。
英単語は毎朝も帰りにやり、学校の宿題も全て平日にやるようにしていました。
そして休日ですが、参考書の英文や古文などを主にやっていました。理由は、時間がかかってしまうため平日にやるとそれだけで終わる可能性があるからです。休日のメリットは時間があることです。なので、なるべく受験科目全てには目を通せるようにしていました。歴史は平日に復讐をする事で、かなり整理されているので一問一答などをやっていました。あとは、英語の音読も時間がかかるので休日やっていました。
まとめると、平日休日の区分というよりは、時間が多くあるかないかの基準で勉強していました。特に歴史は復習しないとどんどん新しい知識だけ溜まってしまうので、なるべくその日のうちにノートにまとめ整理するようにしていました。
コメント(1)
ごぼう
6/24 17:33
ありがとうございます!!参考にさせていただきます