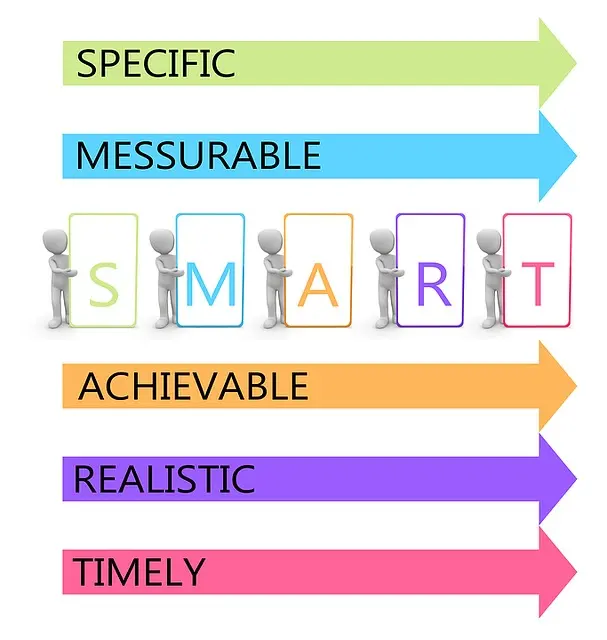偏った勉強時間配分
クリップ(17) コメント(1)
7/19 17:22
UniLink利用者の80%以上は、難関大学を志望する受験生です。これまでのデータから、偏差値の高いユーザーほど毎日UniLinkアプリを起動することが分かっています。
フマーユーン
高3 千葉県 慶應義塾大学志望
慶應義塾大学志望の高3です。私は世界史が好きで土日祝日は3教科合計で14時間やろうとしているのですが、気がついたら8時間は世界史をやっていて、残りの苦手な英語、小論文にかける時間がいつもなぁなぁになってしまいます。時間の配分は気をつけなければいけないですよね?また、英語を英語のまま理解することが慶應義塾大学合格のカギと言われていますが、東進のレベル別長文問題集を解いて、音読をするだけで速読力は身につきますか?
回答
キリンマダラ
慶應義塾大学経済学部
すべての回答者は、学生証などを使用してUniLinkによって審査された東大・京大・慶應・早稲田・一橋・東工大・旧帝大のいずれかに所属する現役難関大生です。加えて、実際の回答をUniLinkが確認して一定の水準をクリアした合格者だけが登録できる仕組みとなっています。
質問者さんに厳しいことを言いますが、落ち込まないで下さい。
質問者さんは勉強をしっかり時間をかけてしている点は素晴らしいですが、落ちる典型的なパターンです。
単純暗記で楽しい世界史ばかりして、苦手な科目から逃げています。
このままでは落ちると思います。
ただ、今回、この質問をしてくれたことによって気が付ける機会になったのではないでしょうか?
慶應で1番大切なのは英語です。英語が苦手だと話になりません。
慶應の英語は早稲田の英語よりも難しいです。そのくらい英語を重視している大学です。
それに対応するためには英語に毎日、1番時間をかけなければならないです。
だいたい、14時間勉強ならば、英語6時間、世界史5時間、その他4時間くらいですね。
10時間勉強ならば、英語5時間、世界史3時間、その他2時間くらいが目安です。
音読だけでは上がりません!多読と演習が必要です!詳しくは僕の他の回答に書いてあります!見てください!
コメント(1)
フマーユーン
7/20 9:18
ありがとうございます!
せっかくの夏季休業ですので、アドバイスいただいた時間配分に気をつけて勉学に励みます!